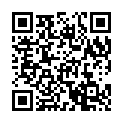秋祭り 山車14台 順不同

建速素盞鳴尊 タケハヤスサノオノミコト
伊弉那岐命(イザナキノミコト)の御子
【町内名】下川岸(したがし)
【飾り物の場面】 八岐大蛇(やまたのおろち)を退治し、奇稲田媛命(くしなだひめ)を救う素盞鳴尊
母のイザナミノミコトが亡くなったことを泣き叫び暴れたため、姉の天照大御神から、高天原(たかまがはら)を追放される。降り立った出雲で、八岐大蛇を倒す。そのとき大蛇の尾から、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ 別名:草薙の剣)を発見する。この剣を天照大神に献上するが後に瓊々杵尊の天孫降臨の際に三種の神器として地上にもたらされる。(草薙の剣は三種の神器の一つ。)ちなみに大蛇を倒した剣は十握剣(とつかのつるぎ)という。
【ひとこと】スサノオの乱暴ぶりを悲しみ、姉の天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸(あまのいわと)に隠れたため、この世が暗闇に包まれたとき、岩戸の前で踊って天照大神の興味を誘い岩戸を開いたのが、「おかめ様」こと「天鈿女命」(あめのうずめのみこと)である。おかめを飾っている山車があるのは夏の本宿祭りの本川岸である。
【人形製作年】江戸後期(伝承)
【人形制作者】不明
【山車製作年】明治31年(1898年 伝承)
【額】宏遠(こうえん)
【下座連】清水芸座連
【彫刻製作者】佐藤光正
【彫刻図柄】日本神話

諏訪大神
大国主の御子
【町内名】上新町(かみしんまち)
【飾り物の場面】 諏訪大神の依代(よりしろ)となる榊(さかき)
諏訪大神にちなんだ山車
その年の新藁を使ってしめ縄をつくり、山車の四方をめぐらしている。これは山車は移動する神座を表すという遺風を、いまに残しているもの。八咫鏡(やたのかがみ)の両脇に旗などが置かれるが、八咫鏡とは「三種の神器」の一つとされているもの。
【飾り製作年】昭和11年(1936年)
【飾り制作者】区民全員
【山車製作年】昭和11年(1936年)
【額】敬神(けいしん)
【下座連】鹿嶋芸座連
【彫刻】成毛哲太郎(伝承)
【彫刻図柄】切り抜きの龍

瓊々杵尊 ニニギノミコト
天照大御神の孫 天孫降臨
【町内名】西関戸(にっせきど)
【飾り物の場面】 三種の神器を携え、降臨する瓊々杵尊
天照大御神の孫であり、天孫降臨神話の主役の神。天照大御神に命じられ、高天原から、葦原中国(あしわらのなかつくに)を治めるため降り立つ。絶世の美女、木花開耶媛命(このはなさくやひめ)と結婚し、生まれた子が神武天皇の祖父または瓊々杵尊の孫が神武天皇とも言われている。秋祭りの町内、仲川岸が神武天皇を飾っているが、人形の製作者こそ違うがどことなく瓊々杵尊と似ているのは偶然か。
【ひとこと】三種の神器とは八咫鏡(やたのかがみ)・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)・天叢雲剣(草薙剣)(くさなぎのつるぎ)のこと。瓊々杵尊が天孫降臨の際に天照大御神から授けられたもの。天皇の証として、皇位承継と同時に継承される宝物である。近年では、式年遷宮のあった伊勢神宮に天皇皇后両陛下が参詣するため2014年3月25日20年ぶりに「三種の神器」のうち、剣と璽(じ、まが玉)が一緒に運ばれた。
【人形製作年】昭和15年(1940年)
【人形制作者】鼠屋(伝承)
【山車製作年】昭和15年(1940年)
【額】神威赫奕(しんいかくえき)明治神宮の宮司(元海軍大将)有馬良橋氏の筆による
【下座連】雄風會
【彫刻】4代目石川藤吉朝光
【彫刻図柄】龍 唐子 獅子群遊

神武天皇
初代天皇 生まれながらにして明達
【町内名】仲川岸(なかがし)
【飾り物の場面】霊剣を授かる神武天皇
瓊々杵尊の天孫降臨後、まだ天下を治めておらず、神武天皇が東征を開始する。熊野の土地の神の力に、軍勢が倒れるが、天照大御神が降ろした霊剣により回復する。
【ひとこと】香取市内東部に鎮座する香取神宮はこの神武天皇の即位ののちに創建されたと伝えられている。ちなみに、香取神宮の主祭神である経津主命(ふつぬしのみこと)を飾っている山車が夏の本宿祭りの荒区である。
【人形製作年】明治31年(1898年)
【人形制作者】湯本長太郎(伝承)
【山車製作年】明治31年(1898年)
【額】博如天(ひときことてんのごとし)
【下座連】佐原囃子連中
【彫刻】後藤直政(伝承)
【彫刻図柄】開墾 田植え 刈り入れ 収穫 菊花 鳳凰

日本武尊 ヤマトタケルノミコト
【町内名】北横宿(きたよこじゅく)
【飾り物の場面】 妃の亡き弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)を思い嘆く日本武尊
山車は鼠屋こと福田万吉の手による日本武尊の大人形と、複数の彫工が競った山車彫刻である。
【ひとこと】日本武尊の持っていた剣は、出雲に降り立った建速素盞鳴尊が八岐大蛇(やまたのおろち)を倒したときに大蛇の尾から出てきた剣。天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ 別名:草薙の剣)という。草薙の剣という別名は、駿河で野火攻めにあったときに、この剣で草を薙ぎ払って難を逃れたため。八岐大蛇とは八つの頭と八つの尾をもつ大蛇。天照大御神によって、追放され出雲に降り立った建速素盞鳴尊により、酒に酔ったところを八つの頭と八つの尾を切り落とされ退治された。
【人形製作年】明治8年(1875年)
【人形制作者】鼠屋伝吉
【山車製作年】明治8年(1875年)
【額】愛國(あいこく)
【下座連】源囃子連中
【彫刻】岸上定吉・塙正明・石川常次郎
【彫刻図柄】猿田彦と楽人 頼朝の放生会と千羽鶴
【欄間】表は天照大神、裏は神功皇后と武内宿禰(たけしうちのすくね)

仁徳天皇 ニントクテンノウ
民の貧窮を救うため税を免除した聖帝
【町内名】南横宿(みなみよこじゅく)
【飾り物の場面】山上から眼下を眺める仁徳天皇
【ひとこと】山車額はどこの町内も書を飾っているが、南横宿の山車には仁徳天皇が詠んだとされる和歌が飾られている。
『高きやに 昇りてみれば煙立つ 民のかまどは にぎわいにけり』
人民の家々から煙が立ち上らないのをみて、3年間課役を免じ自らに質素倹約を課した。飯時に高台に上ってみると、炊煙が立ち上っており詠んだ歌。山車の彫刻は10年をかけて彫上げた三国志。表欄間に劉備、関羽、張飛が義兄弟の契りを結ぶ「桃園の誓い」、蕨手には劉備玄徳と諸葛孔明が彫られている。
【人形製作年】大正14年(1875年)
【人形制作者】3代目安本亀八(伝承)
【山車製作年】明治8年(1875年)
【額】高きやに 昇りてみれば煙立つ 民のかまどは にぎわいにけり
【下座連】あらく囃子連
【彫刻】後藤一重(伝承)
【彫刻図柄】三国志演技 龍

浦嶋太郎
【町内名】下新町(しもしんまち)
【飾り物の場面】亀との別れを惜しむ浦島太郎
子供たちにいじめられていた亀を助け逃がしてあげた浦島、数日後に亀に誘われ、海の底の竜宮城に行く。乙姫の歓迎を受け、遂に3年の月日が経ってしまった。家族が心配になり帰りたいと申し出た。手土産に玉手箱を貰い村に帰ると、地上では700年が過ぎており家族もすでに亡くなっていた。玉手箱には竜宮で過ごした3年間が入っており、あけてしまうと時が戻ってしまう、乙姫にけしてあけてはいけないと言われていたが、過去に戻るのではないかと思った浦島は玉手箱を開けてしまう。美しく楽しかった竜宮での3年間が映し出されたが玉手箱から出てきた白い煙はしだいになくなり、残ったのは白髪の年老いた浦島だった。その後ついには息絶えたとも、鶴になり亀となった乙姫と夫婦になったとも。竜宮伝説 おとぎ話の一つ。
【ひとこと】彫刻の下絵には歌川国芳の「水滸伝錦絵」を使ったようだ。国芳は江戸時代の浮世絵師で山車彫刻が彫られる前年に亡くなっている。彫刻のみならず玉簾も水滸伝で統一されている。当時の玉簾は、ぎやまん(ダイヤモンド?)で玉を作っていたという。山車を囲むしめ縄は本金製である。
【人形製作年】明治12年(1879年)
【人形制作者】鼠屋福田万吉(伝承)
【山車製作年】江戸後期
【額】恩波(おんぱ)
【下座連】牧野下座連
【彫刻】石川三之介
【彫刻図柄】歌川国芳の水滸伝

小野道風
能書家 小野妹子の子孫 花札の絵柄にもなる人物
【町内名】新橋本(しんはしもと)
【飾り物の場面】頑張る蛙を見て、物思いにふける小野道風
自分の才能のなさに、自己嫌悪に陥り、書道を辞めようかと悩んでいたとき、雨の中散歩に出た道風が偶然目にしたのは柳に飛びつこうと何度も挑戦している蛙の姿だった。いくら飛んでも柳に飛びつけるはずがないと馬鹿にしていたが、偶然にも風が吹き柳にうまく飛び移ることができた。これを見た道風は、自分は一生懸命努力をしていないと目が覚める思いをし血の滲むような努力をするようになった。江戸時代中期の浄瑠璃「小野道風青柳硯」
【ひとこと】平安中期の能書家。それまでの中国的な書風から和様書道の基礎を築いた人物。生存当時から、道風の能書の名声は高かったが、没後その評価がますます高まり、「書道の神」として祀られた。源氏物語でも、道風の書が評価されている。
【人形製作年】明治4年(1871年)
【人形制作者】鼠屋福田万吉(伝承)
【山車製作年】明治27年(1894年)
【額】雲龍(うんりゅう)小野道風本人の筆跡と伝えられている
【下座連】野田芸座連
【彫刻】岡野繁
【彫刻図柄】雌雄の龍

牛天神
菅原道真
【町内名】新上川岸(しんうわがし)
【飾り物の場面】牛に乗り、安楽寺の梅を見に行く菅原道真
醍醐朝時代に右大臣まで昇進したが、左大臣藤原時平に仕組まれ、大宰府へ左遷させられ、その地で没する。梅の花をこよなく愛し、左遷される際に、庭の梅に向かい「東風吹かば にほひおこせよ梅の花 主なしとて 春な忘れそ」と詠んだ。さらにその梅の木が道真を追って、一夜のうちに大宰府へ移動したという。
【人形製作年】江戸後期
【人形制作者】不明
【山車製作年】明治45年(1912年)
【額】上河岸(うわがし)
【下座連】潮風會囃子連
【彫刻】不明
【彫刻図柄】源三位頼政

大楠公 ダイナンコウ
楠木正成(くすのきまさしげ) 勤王
【町内名】東関戸(ひがしせきど)
【飾り物の場面】桜井の別れの楠正成 戦死を悟った父、息子との別れの場面
鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将で、鎌倉幕府を倒すため挙兵した後醍醐天皇方につき戦った。絶望的や状況下で出陣し最後は歴史上最も激しい戦いと言われる湊川の戦いで敗れ、弟の正季(まさすえ)と刺し違える。正季らとの最後の願い、七生報国 (しちしょうほうこく)「七たび人と生まれて、逆賊を滅ぼし、国に報いん」は後に旧日本軍の精神として受け継がれ特攻隊にも唱えられたという。
【ひとこと】正行との桜井の別れが有名。桜井の別れは古典文学『太平記』の名場面で、戦前教育を受けた者には有名な話。大楠公の佩刀は小竜景光(こりゅうかげみつ)と伝承されており、明治天皇に献上、国宝に指定されている(東京国立博物館)。下分とともに下座は『桜井の別れ』を演奏する。『桜井の別れ』とは日本の唱歌の一つで、大楠公と小楠公の別れを歌った悲しい歌詞。戦前に歌われた唱歌。
【人形製作年】昭和10年(1935年)
【人形制作者】大柴護豊
【山車製作年】昭和10年(1935年)
【額】純正(じゅんせい)陸軍大将の荒木貞夫の筆による
【下座連】東関戸連中
【彫刻】金子光清・池田信之・北沢一京、秀太
【彫刻図柄】南北朝時代「太平記」

小楠公 ショウナンコウ
楠木正行 まさつら 正成の子 辞世の句
【町内名】下分(しもわけ)
【飾り物の場面】如意輪寺(にょいりんじ)の門扉に辞世の句を書きとめる楠正行(くすのきまさつら)
大楠公(楠正成)の嫡男。父の後を継ぎ、南朝方として戦う。父の遺言でもある得意の山岳戦の策を待ちながらその戦術を知らない天皇側近に急かされ圧倒的に不利な状況で、四条畷(しじょうなわて)の戦いに臨み、死闘の末に弟の正時と刺し違えて自害する。この戦の前に、吉野の如意輪寺に「かへらじと かねて思えば梓弓 なき数にいる 名をぞとどむる」と辞世の句を残す。
楠木正成が明治政府により「大楠公」として神格化されたため、父の遺志を継ぎ命を落とした正行も「小楠公」と称された。
【ひとこと】大楠公(だいなんこう)は父であり、東関戸区の山車の飾り物となっている。山車の飾り物(大人形)の制作年も製作者も同じく大正10年である。東関戸区とともに下座は『桜井の別れ』を演奏する。
【人形製作年】昭和10年(1935年)
【人形制作者】大柴護豊(伝承)
【山車製作年】明治28年(1895年)
【額】下分(しもわけ)
【下座連】潮来芸座連
【彫刻】不明
【彫刻図柄】

源頼義 みなもとのよりよし
武勇
【町内名】下宿(しもじゅく)
【飾り物の場面】山中の戦いの中で、岩を弓で砕き水を出したという故事による
【ひとこと】平安時代中期の武将。河内源氏初代棟梁。源義信の嫡男で河内源氏2代目棟梁。後の有力、名流とされる武将の多くが頼義が祖。弓の達人で若いころから武勇の誉れ高く後に陸奥守・鎮守府将軍となる。前九年の役の時に、水に困り敗戦しかけるが源氏の氏神である八幡神に祈り弓で岩にを突くと水が出て窮地を脱した逸話がある。無事に凱旋出来たことから京都の石清水八幡宮を分霊し、壷井八幡宮と鎌倉の鶴岡八幡宮を創建した。
【人形製作年】明治32年(1899年)
【人形制作者】古川長延
【山車製作年】明治8年(1875年)
【額】誠意(せいい)
【下座連】分内野下座連
【彫刻】石川三之介 後藤源兵衛 左重吉 後藤桂林
【彫刻図柄】

鎮西八郎為朝
弓の名手 源義経の父の、源義朝の弟。
【町内名】上中宿(かみなかじゅく)
【飾り物の場面】鏑矢(かぶらや)を持ち、構える鎮西八郎為朝
【ひとこと】為朝は勇猛で荒くれ者、身長は7尺(約2m70cm)の巨漢、弓の名手であり、弓を引き続けた結果、左腕だけ4尺(12cm)も長いという。幼少期より荒くれ者であった為朝は、父に勘当され、13歳で九州に追放される。為朝の弓は5人張りの弓で、放つ矢は鎧さえ貫通し敵将2人を串刺しにするほどの威力。命中精度も高く兄の義朝の兜の星を命中させた。山車の彫り物は「柱隠し」という技法で富士の裾野での巻狩りの様子が彫られており、柱をうまく隠している。
【人形製作年】明治15年(1882年)
【人形制作者】鼠屋福田万吉(伝承)
【山車製作年】嘉永5年(1852年)
【額】富士山の彫刻
【下座連】和楽会
【彫刻】立川録三郎(伝承)20人の下工を連れ、3年佐原に住み込みで仕上げたという。
【彫刻図柄】源頼朝の富士の巻狩り

源義経
【町内名】上宿(かみじゅく)
【飾り物の場面】壇ノ浦の源平の戦いでの雄姿
【ひとこと】色白で小柄であったと言われる。元服前の名は牛若丸。鎌倉時代の武将。母は常磐午前で絶世の美女という。平治の乱後、常磐とともに平清盛に捕えられ殺されるはずだったが、常磐の美貌に惚れ込んだ清盛が、妾となる代わりに子供らを仏門にいれて命を許された。義経は鞍馬寺に預けられたが父が清盛の軍に殺されたと知った義経は打倒平氏を胸に鞍馬寺から逃げ出す。異母兄の源頼朝が挙兵したことを知り、馳せ参じ涙の対面を果たした。壇ノ浦の戦いで平氏方が優勢であったが義経らしい奇策でなんとか持ちこたえた。平氏には平清盛の妻二位尼と幼少の安徳天皇がいたが、三種の神器の一つ宝剣を胸にだき入水自殺を図った。父の殺害を知った日から平氏打倒を内に戦ってきたが、源平合戦はついに源氏の勝利で終わった。平氏を滅ぼしたが許可なく官位を受けたことや、戦いでの独断専行で頼朝の怒りを買い対立。頼朝の追討を逃れ各地を転々とするが、31歳の若さで自害する。
【人形製作年】昭和55年(1980年)
【人形制作者】田口義雄
【山車製作年】昭和53年(1978年)
【額】智勇(ちゆう)
【下座連】寺宿囃子連
【彫刻】石川寅次郎(伝承)
【彫刻図柄】獅子の子落とし 唐獅子牡丹 波千鳥
山車の掲載順序について
飾り物の登場時代の順に掲載しています。山車の顔ともいえる山車人形の題材の場面や背景について、なんとなく知っているというものが多いと思います。ではその題材はどんな場面なのか、説明出来るかというとあまり深くは知らないものです。人形だけでなく、彫り物や額などについても紹介しなお一層佐原の大祭を楽しんでいただけるよう心がけました。