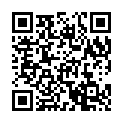夏祭り 山車10台 順不同

伊弉那岐命(イザナギノミコト) 田宿(たじゅく)
国造りの神で日本国土を形づくる神や森羅万象の神を多数儲ける。
【飾り物の場面】鶺鴒(せきれい)から子作りを学ぶ伊弉那岐命
伊邪那美命(イザナミノミコト)が火の神を生んだときに火傷を負って亡くなると、その神を切り殺してしまう。妻に会いたい気持ちで見てはいけないという約束を破り黄泉国で妻を見てしまい怒りを買い完全に離縁する。黄泉国(よもつくに)の穢れを禊した際に、天照大神、月読尊、素戔嗚尊(すさのおのみこと)などの神が生まれた。諏訪神社秋祭りの下川岸の山車が素戔嗚尊を飾っているいる。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】
天鈿女命(あめのうずめのみこと) 本川岸区(ほんがしく)
大国主の御子
【飾り物の場面】天の岩戸の前で踊る天鈿女命
スサノオの乱暴ぶりを悲しみ、姉の天照大神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸(あまのいわと)に閉じこもった時に、この世が暗闇に包まれ、神々は大いに困り岩戸の前で様々な儀式を行った。その際、天鈿女命が岩戸の前で力強く踊り神々が喝采した。天照大神は外の騒ぎが気になり岩戸を開きこの世に光が戻った。天孫降臨の際に瓊々杵尊(ニニギノミコト)の御供をした。猿田彦命(さるだひこ)は先導し高千穂に降臨した。瓊々杵尊は諏訪神社秋祭りの西関戸の山車の飾り物。猿田彦命は西関戸と東関戸が分かれる前の関戸郷の山車の飾り物であった。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】

武甕槌尊 タケミカヅチノミコト 浜宿
雷の神、剣の神 鹿島神宮の主神
【飾り物の場面】国土平定をする武甕槌命
「出雲の国譲り」で、十掬の剣(とつかのつるぎ)を波の上に逆さに突き立て、その切っ先の上に胡坐をかいて、大国主に対して国譲りの談判をおこなった。このとき国譲りの交渉を行ったのが武甕槌尊と経津主命(フツヌシノミコト)の二神である。また後に、神武天皇の東征の際、熊野で神武軍全軍が気を失って倒れるが、天照大神らの命により武甕槌尊の布都御魂(ふつのみたま)を神武に授け、悪霊らを倒している。経津主命は本宿夏祭りの荒区の山車である。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】

経津主命(ふつぬしのみこと) 荒区
香取神宮の祭神
【飾り物の場面】国土平定をする経津主命
伊邪那美命(イザナミノミコト)が火の神を生んだときに火傷を負って亡くなったため伊弉那岐命(イザナギノミコト)が火の神を斬り殺した後、剣から滴る血が固まって、経津主命が生まれる。日本書紀では武甕槌尊と共に国譲り、国土平定をしたという。武甕槌尊が神武東征の際に自分の分身として降ろした剣と同じ名前を持つ。古事記では武甕槌尊の別名とも言われている。
【ひとこと】香取市内東部に鎮座する香取神宮はこの神武天皇の即位ののちに創建されたと伝えられている。ちなみに、香取神宮の主祭神である経津主命(ふつぬしのみこと)を飾っている山車が夏の本宿祭りの荒区である。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】

神武 船戸
初代天皇
【飾り物の場面】東征の際、八咫烏(やたがらす)に導かれる神武天皇
八咫烏とは、熊野国から大和国への道案内をしたとされる3本足のカラス。神武天皇は諏訪神社秋祭りの仲川岸も神武天皇を山車に飾っている。45歳のときに東征を開始するが、熊野では、土地の神の力に倒れるが、武甕槌尊と経津主命により回復。八咫烏の案内で山路を抜け、長髄彦(ナガスネヒコ)の戦では「金鵄(キンシ)」と呼ばれる「金色の鳶(トビ)」に助けられ天下を平定する。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】

菅原道真 下仲町
平安時代の学者・政治家・学問の神様
【飾り物の場面】梅を愛でる菅原道真
醍醐朝時代に右大臣まで昇進したが、左大臣藤原時平に仕組まれ、大宰府へ左遷させられ、その地で没する。梅の花をこよなく愛し、左遷される際に、庭の梅に向かい「東風吹かば にほひおこせよ梅の花 主なしとて 春な忘れそ」と詠んだ。さらにその梅の木が道真を追って、一夜のうちに大宰府へ移動したという。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】

金時山姥 寺宿
坂田金時とその母 幼名は金太郎
【飾り物の場面】熊にまたがり馬の稽古をする金太郎と山姥
京都の武士であった父が敵に殺され、母は敵から逃れるため金太郎を連れ山奥に隠れて暮していた。金太郎は足柄山で、クマと相撲や馬の稽古をしながら毎日を過ごしていた。動物たちと山を探検していたときに、崖のしたの急流に木を押し倒し橋をかけた。それを見ていた源頼光に力量を認められて家来になり、後に酒呑童子(しゅてんどうじ)を退治。坂田金時という名の武士になり、源頼光の四天王となる。下座は童謡「金太郎」を演奏する。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】

大田道灌(おおたどうかん) 上仲町
【飾り物の場面】鷹狩りをする大田道灌
室町時代後期の武将。摂津源氏の流れを汲む。江戸城を築城した武将。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】

鷹 仁井宿(にいじゅく)
【飾り物の場面】稲ワラと竹で作られた鷹
重さ400キロ、長さ7メートルもある大鷹は、足爪を軸にやじろべーの原理でバランスを取っている。民俗伝承文化財である鷹の制作は、1758年頃より伝わっている。鷹を作るときは町内総出で数年に一度制作されている。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】

鯉 八日市場
【飾り物の場面】稲ワラ等で作られた鯉
麦藁細工。全長7メートルで口や胸ビレが動く仕掛けになっている。町内総出で制作されている。かつては祭りのたびに作られ、終われば焼却されていた。
【人形製作年】
【人形制作者】
【山車製作年】
【山車製作者】
【額】
【下座連】